三菱自動車のクルマはどのようにして造られているのでしょうか。調査、企画、デザイン、設計、試作、テスト、購買、生産、物流、販売という一連の工程があり、それぞれの工程を高い技術力を持ったプロフェッショナルたちが担っています。本シリーズでは 各職場で働く人々を紹介していきます。今回は、世間をアッと驚かせた、小型車(5ナンバー車)*1の枠を超えた上級4ドアハードトップ*2『ディアマンテ』の商品企画を手掛けた商品戦略本部・本部長付の小島正人さんに話を聞きます。
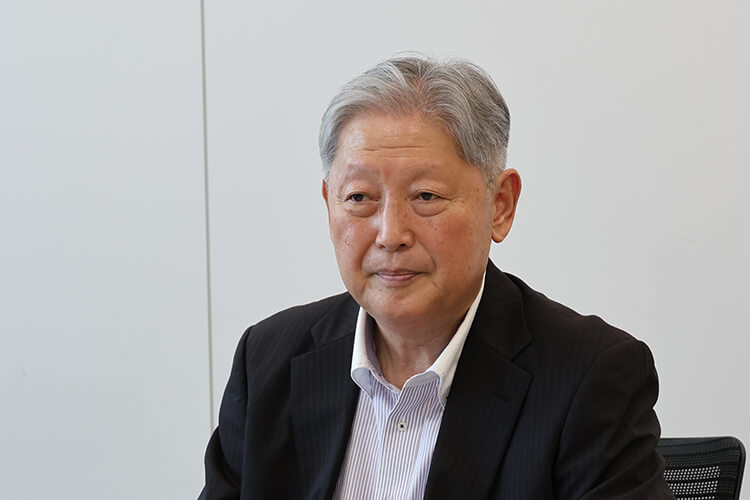
『ディアマンテ』は、三菱自動車が1990年5月に投入した新型上級4ドアハードトップ車です。当時主流だった5ナンバー車とは一線を画す3ナンバー(普通車)専用のワイドボディを採用し、堂々としたフォルムと高級感のある佇まいで、上級セダンを求める顧客層のニーズに応えつつ、5ナンバーの競合車と対抗する価格を実現し、幅広い顧客層から支持を得ました。三菱自動車で2度目の「日本カー・オブ・ザ・イヤー」も受賞しています。税制改革による自動車市場の変化を予測し検証を重ね、競合他社に先んじてワイドボディで開発を決心した『ディアマンテ』は、90年代以降の国内市場の構図を変えた、正に「ゲームチェンジャー」と呼ぶにふさわしい一台です。
さらに、2.5リッターV6エンジンによる力強い走りに加え、ゆとりと上質をテーマにしたインテリアには本木目パネルや、純毛(ウール100%)生地のシートなども備え、クラス初のフルタイム4WDや独自のトラクション・コントロール・システムなど三菱車らしい先進技術も搭載されていました。
- *1 小型車(5ナンバー車)とは、日本独自の車両規定で、全長4.7m以下・全幅1.7m以下・排気量2.0L以内で作られた車両。このスペックの何れかが超えると普通車(3ナンバー車)となり、89年4月以前は、新車価格に含まれる物品税や、毎年支払う自動車税、任意保険料などが5ナンバー車よりも大幅に高額になるため需要が極端に低く、国産車は高級セダンでさえ基本ボディーは小型車枠で開発されていた。
- *2 4ドアハードトップとは、4ドアタイプながらも窓枠がないクルマのこと

『ディアマンテ』
「学生時代から三菱車のファンで『ランサーEX』に乗っていた」という小島さんは、82年三菱自動車に入社、84年からは西東京三菱自動車販売に出向し新車のセールスを担当。87年、28歳で本社に復職後、乗用車商品企画部に所属し、2004年・45歳まで個別車種の商品企画に携わった。最初に企画を手掛けたのが『ディアマンテ』だった。
「日本経済が膨らみつつあった1980年代、国内市場では上級車需要の拡大が目覚ましく、当時、他社では系列チャネルの兄弟車も含め年間60万台も売っているクルマがありました。上級車市場に我々もなんとか食い込もう、そのためには対抗できるクルマを造らなきゃいけないというのが開発の狙いでした。その頃、三菱自動車には『ギャランΣ(シグマ)』という、室内の広さを売りにしたクルマがありましたが、商品選択の決定打に欠けており、上級車ユーザーの期待に応えるためには、内外装の質感向上に加え、エポックメイキングな特徴を備えたクルマを投入する必要がありました」
小島さんには、販売店でセールスマンをしていた頃の忘れがたい経験があった。
「販売店で僕はその『ギャランΣ』を一生懸命売り込んでいました。あるとき、商談で他社と激しく競合したことがありました。何度もお客様のもとに足を運び、『ギャランΣ』のセールスポイントだった室内の広さを丁寧に説明し、かなりの値引きも提示して、支払総額では競合車に対して50万円も安くできたのです。それでも、お客様が選んだのは競合車でした。
お客様から、『小島さんからは、相当にお買い得な価格を出していただきましたが、お金じゃないんですよ』と言われ完敗でした。この経験から “お客様にとって本当に価値ある商品とは何か” をもっと突き詰めなければいけない。まずは競争の土俵に立てる商品を造らなければだめだと思ったのです。そして、そうしたクルマができれば、価格を下げずとも適正な価格で売ることができるとも実感しました」

『ギャランΣ』
商品ラインアップや個別モデルの企画を担う商品戦略本部の人員は、現在120人超に増強されているが、当時は今の4分の1ほどの部隊であったという。
「今よりも少ない人員で、より多くの車種を開発・販売していた時代でした。クルマが好きだからこそできた、そんな熱量に満ちた日々だったと思います。商品企画の仕事は企画書の発出が最大のタスクですが、それだけで完結するものではありません。私たちだけではクルマは造れません。企画書を作り、開発やデザイン、営業など各部門の担当者に企画の意図を丁寧に説明し、皆の共感と理解を得て、ベクトルを合わせて取り組まなければ、お客様の心に響くクルマにはならないのです」
小島さんたちが目指したのは、どのようなクルマだったのか。
「当時、国産高級車や海外ブランド車の購買層は、自営業や医師などクルマの一部の費用を経費で処理することもできる方々でした。一方で上級車の購買層は、企業の課長や部長クラスの勤め人が多く、購入費用や維持費に非常に敏感な層です。しかし、両者がクルマに求めるイメージは共通しており、『落ち着きがあり、風格があり、安定感のある車格の高いクルマ』を求めていました。上級セダンで高級車にも引けを取らない車格感を持つエポックメイキングなクルマを実現できれば、このセグメントに後発の三菱自動車でも勝負になる。企画・開発・デザインのメンバーの意識がしっかりと方向性を共有し、勝負できるクルマづくりに挑んだのです」
どうしたらよいか。具体的なアイデアが次々と浮かんだ。
「当時の国産の上級車は5ナンバー車(小型車)で、細長いクルマでした。比べて、海外ブランド車は、ワイドボディで、もっと堂々としたフォルムでしたので、そうしたクルマを造るのはどうか、というアイデアが出ました。さらに高級感や上質感だけでなく、三菱自動車ならではの強い走りを求めるならこういう手があるのではないか、とか、デザインはどうだとか。商品企画、開発プロジェクト、デザインの3つの部署がチーム一体となって議論し、アイデアを出し合ったわけです。いいメンバーに恵まれました」
企画の方向性は、ワイドボディの3ナンバー(普通車)のクルマを造ることで固まった。しかし、そこには大きな壁があったのだ。
「当時、私たちは大いに悩みました。3ナンバーのワイドボディ専用車を開発するというのは、当時の常識では“あり得ない”挑戦だったのです。しかし、圧倒的な人気を誇る競合の上級車に後発で挑む以上、それらを凌駕する魅力を提示しなければ勝負になりません。その有力な方策が、5ナンバー枠を超えるワイドボディの採用でした。これにより、堂々としたスタイリングと広々とした室内空間、そして走りの質感向上は実現可能と考えたのです。 しかし、当時は消費税ではなく物品税の時代。3ナンバー車には非常に高額な税金が課されており、自動車税や任意保険料も跳ね上がる状況でした」
チームは原寸大のデザインモデルを製作し、社内外で繰り返し調査を行った。3ナンバーのワイドモデルは「かっこいい」「買いたい」と高い評価を得たが、購入にかかる費用を提示すると、途端に「買えない」という声が多数を占め、結果は一変した。
「これでは、造っても今は売れない。粘りに粘って検証作業も重ねて来ましたが、いよいよ決心しないと開発が間に合わなくなってきました」
初期構想から約1年が過ぎ、発売時期も当初予定の89年から90年に延びていた。87年秋、いよいよ決断のタイムリミットとなり、結果、3ナンバー車は諦めた。
「5ナンバーのナロウモデルで開発するという苦渋の決断に至ったのです」

お客様のニーズに応えるために、常識的な範囲で戦うことを捨てて新しい提案を
やむなく当初の企画は断念せざるをえなかったのだが、それから1か月が経った頃、87年11月末、朝の通勤途中に山手線の中で新聞を読んでいた小島さんは愕然とした。その1面に、「EUが日本の3ナンバー車に対する高額な自動車税や任意保険料は、欧州車に対する非関税障壁であるとして、GATT*3に訴える」という内容の記事が躍っていたのである。小島さんは「マーケットの潮目が変わる」と直感した。税制が変われば、3ナンバー車の諸経費は抑えられる。
「ワイドボディにすることでかかるコストはそれほどでもない。会社に着くや、すぐさま開発プロジェクト、デザインとも連携して、もう一度、3ナンバー車による需要開拓の可能性、開発日程、費用への影響、デザインの方向性の見直しを詰め、12月、その資料をもって当時の社長に直訴したのです。『5ナンバーでの開発をストップして、もう一度、3ナンバーでやらせて下さい』と。社長は『もう一回チャレンジしてみろ』と言ってくれました」
88年3月、3ナンバー車での開発再スタートが正式決定される。発売まで26カ月のタイミングだった。89年には消費税が導入され、物品税が廃止された。3ナンバーでも5ナンバーでも購入にかかる税率は同じである。自動車税も排気量ランクのみになった。結果、3ナンバー車であっても対抗していた他車と同じ価格帯で販売できることになったのである。試作車の制作など、開発コストもかけていたが、ターゲットとするお客様の真のニーズに応えるクルマを出すことを優先した。
まだこの新車には名前がなかった。最終的には社長決裁になるが、ネーミングも商品企画の仕事である。『ディアマンテ』と名付けた由来とは。
「ここ一番の勝負をかけて投入するのだから、三菱を代表する、“ダイヤモンド”を使ったらどうかという声が出ました。ただ、ダイヤモンドの商標登録はすでに押さえられていて使えなかった。すると、『ディアマンテ』はどうだ、スペイン語でダイヤモンドだと言ってきた人がいた。調べると、昭和40年代に当社ですでに登録していた。驚きましたけど、結果的にマーケティングしやすい名前でした」
満を持して、90年5月、『ディアマンテ』は発売された。反響は凄まじかった。
「3ナンバー専用の本格的なワイドボディの上級ハードトップ車でありながら、5ナンバー車と対抗する価格で出てきたのですから、他社も『まさか三菱自動車がここまでやるとは』と思ったことでしょう。発売直後から受注は急速に立ち上がり、瞬く間に1万台の注文がありました。当時、上級グレードには内装に贅沢な本木目のパネルを使っていましたが、材料が足りなくて納車まで1年待ちになっていました。
毎日、販売店からレポートが届くのですが、高級車ユーザーが多数来店しているというのです。価格帯は200~350万円程(税抜き)でしたが、上級グレードには高級車にも引けを取らないV6・3Lエンジン、フルタイム4WDや安全装備も満載しました。それだけ価値ある一台を提供したことで、上級志向のお客様から圧倒的な支持を得ることができたのです」


90年11月、『ディアマンテ』は三菱車として2回目となる「第11回カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。それから30年を経て、今では日本のセダンタイプのクルマは3ナンバーのワイドボディが当たり前になっているのだから、『ディアマンテ』はまさに日本の新たな上級車市場の扉を開いた名車といえるだろう。
小島さんは「ライバルと戦うためには、既存の枠を超えた発想で“ゲームチェンジャー”となるクルマにすることが重要でした」と語る。彼が考える三菱自動車らしさとは――。
「私達の立ち位置も考えれば、既存のカテゴリーとかヒエラルキーに縛られずに、自由な発想で新しい価値を創造し、お客様に提案して行くことこそが三菱自動車らしさだと思います。そして、それが出来るのが三菱自動車の強みです。
例えば、初代の『パジェロ』は、それまでプロユースが中心だった四輪駆動車にレジャーという新しいシーンや使い方を提案して、全く新しい市場を切り拓きました。『ディアマンテ』も、5ナンバーという常識を捨てて上級車の新しい価値を提案した。それが三菱自動車です。これからも、特に若い人たちには枠にとらわれない挑戦を続けて欲しいと思っています」

小島さんは、以来、初代『パジェロ・ミニ』、『ディオン』、『アウトランダー*4』などを手掛け、15年、商品戦略部長に就任。19年商品戦略本部・本部長補佐となり、現在、本部長付となっている。小島さんは、その後の画期的なクルマとして、世界初の量産電気自動車『アイ・ミーブ』と『アウトランダーPHEV』を挙げる。次回は、その『アウトランダーPHEV』の開発に携わった社員の話を紹介しよう。
- *3 GATT: General Agreement on Tariffs and Trade。1947年に締結された国際的な関税及び貿易に関する一般協定
- *4 アウトランダー: 日本国内では『エアトレック』として発売
2025年10月

